2021年より再開の頁です
以前から書いていたプログを、執筆のために休止していましたが、長いことかかった原稿がなんとか終わるので、こちらにこれまでに書いた短文のエッセイを集約することにしました。テーマは、私自身の色々な体験と暮らし方が主ですが、時々お読み下されば嬉しいです。
✿やっと長文の原稿の縮小がなんとか終わり、これから出版に向って動かなければ…….10年前から書き続けた原稿を1/3に縮めるのはちょっと悲しい。タイトルにも苦労しています。フローラ(植物)の文芸書です。日本の古典書から外国語書籍まで色々な本を読みました。
現在、若い新人が多くの斬新なテーマの小説を書いていることに感心します。
● この次は以前に、「マジックバス」でロンドンからギリシャ経由、インドまでの旅の楽しい話を予定。
静かなるエッセイ 「本の捜査探偵」
読書にふさわしい季節になると、私の視線はいつも本棚にいく。下から二段目の右端にあった本。私が子供の時、父の本棚の同じ位置にあったそれは、『エミリアンの旅』と『子を貸し屋』。題名と内容だけが心に残った。
著者を知りたいと思ったのは、〃本の探偵〃を仕事にしている人が現れたからだ。そうか、探偵に頼むと、本について知りたいことを調べてくれるのか。早速依頼すれば良かったのだがそのままになっていたある時、たまたま行った図書館でその本を見つけたのである。復刻版のその童話の作者は、宇野浩二だった。
思いでの中ばかりでなく気になる本はどんどんたまっていく。本屋さんに走り、図書館を巡っているうちに、そこでまたまた気がかりな本に出会う。すると追求するべき本が増える。探偵に頼んでも追いつきそうにもない。そこで自分が探偵になって、私はいろいろな図書館を捜査に訪れた。
捜査までしなくては手に入らないのは、本が古いか外国の本の場合である。本は言葉で出来ているから、書かれている言葉を読めなくてはならない。私は英語とフランス語なら分かるから、捜査線上には、英国か米国の図書館が浮かぶ。
日本でも外国でも、古い図書館を訪れるのは、胸躍る興奮と緊張感を感じる。貴重な本がたくさんある驚きと、ここで勉強した先人たち=かの著名な作家たちのことを忍ぶからだ。同じ場所に私もいる、けれど……、だから……と、気持ちばかりが一杯になって、肝心の捜査になかなか手が出ない。探偵もつい理性を失う。
そのようなもどかしさを感じたのは、ロンドンの大英博物館の中の図書館にいたときだった。丸いドームの天井の下の、金縁に皮表紙の厚い古書に取り囲まれた閲覧室で、私は茫然自失してしまったのだ。ここにいるという感動とその重厚さに圧倒されてしまって。さて気を取り直して捜査に入ると、なんと百発百中。というのも、司書と呼ばれる協力者のお陰であった。
実は〃本の探偵〃とは、図書館で言えばレファレンスの係りの人である。適格な指示の元に捜査、いや探索していくと、必ずおたずねものを射止めることができるのである。大英図書館でも、ずいぶん大勢の方々にお世話になった。見つかると私の手をにぎりしめ、よかった、よかった。こんな司書の方は初めてだったが、よく見るとあちらこちらで、司書と閲覧者がこんな喜びを表現しているではないか。司書の方の仕事への情熱から、文化の深さのようなものを感じたしだいである。
実は若き日、私も大学書館で働いたことがあった。けれども苦手な工学部だったせいか、本自体があまり好きになれなかったのは残念至極。今、利用者になってみて、こうして世界中の図書館のお世話になっている。どんなに有り難いことか、重々身に染みている。
気になる本がたくさんあることもまた幸せなことなのである。本の探偵が続く限り、「孤独から救われる」ーーC・S・ルイス

静かなるエッセイ 「夕顔の開く刻」
あの真っ白く大きな「夕顔」が花を持ち始めていた。よじれてとんがった蕾がぬっと出ていたのを、何日か前、裏口の小さな花壇に見付け、さあ、開花の瞬間を見るぞ、と決心していた。
ウリ科の夕顔の開花を見ることの使命感は、白洲正子の随筆「夕顔」を読んだからだ。白洲は花が全開するのを忍耐強く待った。
朗読の会で私はこの「夕顔」の文章を朗読したので、その練習を何十回したことか。ほぼ暗記したくらいなのに、すぐに忘れてしまうのだ。私は2度も機会を逃してしまった。が、3度目のチャンスを花がくれたのか、もう一つの蕾を見付けた。昼間見たら、夕顔の一本の茎(直径1センチもある)に、最後の蕾が一つある。今度こそ、開花の有様を見逃さないようにしよう。と、手ぐすねを引いて待っていなければならない。
空が暮れなずむまで絵の彩色に夢中になっていて、はっと夕顔のことを思い出した。外は薄く明るい。5時40分。急いで裏口に駈けてゆき、ドアを開くと、ああ、そこに夕顔の白い顔が艶然と微笑んでいるではないか! しまった、また遅れをとった! あのよじれた蕾がゆっくりと逆に回転して、緩やかにその衣を解く様を見たかったのに……。
5センチくらいの長さだった茎は、花底まで9センチにも伸びていた。がっしりした茎に、花茎13センチの花の葩(ひら)が湛然としている。それは夜の闇の中で月のようだ。五片の花びらが一つに繋がったその浅い露斗形は、平たくした朝鮮朝顔の花と似ている。蕊は花の寸法に対しては小さく、おまけのようにちょこんと付いている。
こうなったら、昼間に見た萎んだ姿になるまで見張っていよう。と、何度も見に行った。が、翌朝の5時、7時になっても夕顔は依然として同じ花のままだ。
そうこうするうちに、淡い朝日が霧のようにたちこめ始めた。すると上側の花びらが自らを内側にくるみ始め、徐々に、少しずつ、下方の花びらも包みこんでいる。花の裏側の線が、若草色に色づいて表に浮き出ている。微光を受けて、花はその色を陽の色に染めている。
10時をすぎる頃になると、花は半分までたたみ込まれた。そしてやがて5センチほどの直径の握り拳と化した。
この花が大きな種と成り、それを土に埋めて、来年こそ、蕾から花開くまでを見守り続け、夕顔の花を拝顔する日まで、私の心の中にずっと幻想の花ガ咲き続けているだろう。だが同時に、心の中には「怠慢・失敗」という根も張り続けているにちがいない。
静かなるエッセイ 私の宝石 その価値は
私の小さい時からありすぎた趣味の中でも、今でも好きなのはアンティークを見ること。もちろん、買えればそれに越したことはないが。
絶頂期だったのは、ロンドンに住んでいた頃だ。私は、ほとんど毎日、どこかのアンティック市場をうろついていた。近所に住んでいたポートベロー、ケンジントン・マーケット、カムデン・タウン・マーケット、エンジェル・アンティーク・マーケット、チェルシー・アンティーク・フェア、キングス・ロード・エッセンス、など。それにクリスティーやサザビーなどの競りにも行って見ていたこともある。
と言うのには、日本の友人から買い付けを頼まれたことも一因している。あ
る人はアンティーク・ドール。ある人は、アクセサリー。私は専門書を買って勉強もした。それは、今に遺された品物から歴史を勉強することで、とてもおもしろかった。その頃ロンドンで知り合った日本人の業者の何人かは、今や日本で著名なお店を持っている(現在は不明)。
友人の買い物は結構高価な品だったが、私自身の買い物は安物ばかり。アクセサリーやバッグや布などである。今はそれらを身に着けるのは、よほどの儀式的会合の場合だけだが、私にとっては二度と無い、時と場所の遺品として貴重な宝石なのだ。
金や燻銀の台に七色のガラス球が施されたブローチは、アールヌーボー風。実際に服につけるのはシンプルな服しかない時、あとは手のひらに載せて見るだけ。親しい方に戴いたアメジストの短いネックレスは、遠く離れたその方と、共にありたいときに付けてみる。
ハンドバッグは、ベルべットの地に金銀の糸で刺繍をしてあるもの。レース地にガラス球が織り込まれたのや、30年代のアールデコ風のや、そんなバッグもまた、観賞用だけにはしない。あるバーティーでは、着物を着て持った。
もっとも、ロンドンに住んでいた頃は、そんな物でもちゃんと身に着けていられたのだから、環境というものは人を、独創的にも没個性的にもしてしまうのだ。引き出しの中から、時々取り出して眺めていると、自由を謳歌していられた時代と場所が蘇ってきて、胸がじんとなる。アンティークの役目だろう。
でも今、ロンドンとは違う環境の中にいて、この環境にふさわしい宝石を探している。今私が住む日本の、昔からの農村で求める宝石。遺跡発掘? いやいやそんな大それたものではない。野や森の中で見つける、大地という歴史が持つアンティークである。
紫水晶はムラサキシキブの実。長い一本の枝にたわむように群れついている姿は、三連か四連のネックレスになりそうである。ルビーはガマズミの実。燃えるような透明な石が、丸く集まってついているブローチ。珊瑚はマユミの実。珊瑚色の真ん中に真っ赤な点があるので、ボタンにすればお洒落。瑠璃はサワフタギの実。四つか五つ繋がっているのを二本で、イヤリングになる。こうして自然の中を探せば、イマジネーションの宝石は無尽蔵。 ただしこの宝石は、秋にならないと着けられないのだ。そして毎年新しくなるから新品である。
アンティークの宝石と言わずとも、誰もが心の中に、思い出をしまってある。その思い出を、アンティークとして遺せるかどうかは、価値観による。私は、光るものもくすんでいるものも、美しい宝石として大切にしている。
そして最も大切な一番のアンティークの宝石は、家族はもちろん、私の人生で出合った多数の友人知人お世話になった人々、会ったことがなくても、私に人生上の教えを与えて下さった未知の人々や書籍や音楽である。
書くことについて………梶井基次郎に学ぶ
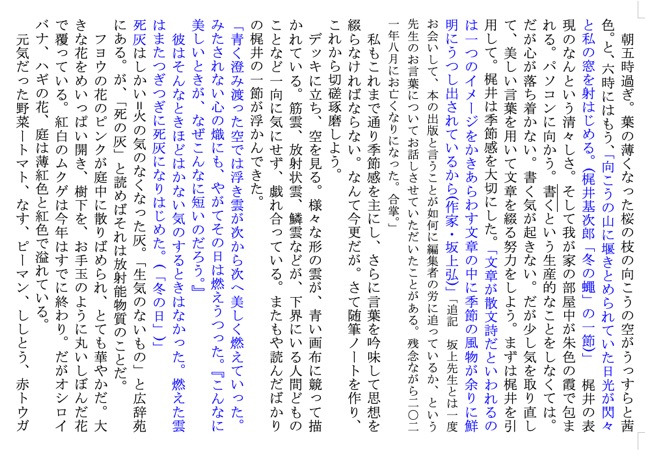
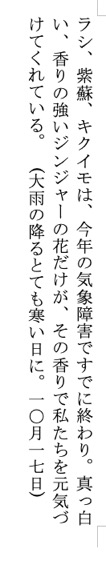
キクイモの話。賢治とともに。(私のツィッターはこの後にあります)
「菊芋の効用 宮沢賢治の話」 鶴田 静著

「このキクイモには、イヌリンていう成分があって、糖尿病に利くんですって。」
農家のぉばさんにこう進められて根茎の入つた袋を1ついただいた。からだは健康この上なかつたから、からだのために食ベ るというつもりではなかつたその花が好きだつたのだ。
それはキク科のキクイモで菊芋である。黄色い花の形はコスモスやヒマワリと同じだ。農道を彩る黄色のコスモス型の花に魅せられて、五、六個を埋めておいたら、何と年々増え、今ではわが丘の丘陵を縁どるほどになつた。がっちりとした逞しい花を寄せ集めて大壺に投げ入れると、そこは、太陽が降りてきたように朋る<なる。
キクイモは、朋治時代に家畜の飼料として原産国の北米から移入された。生姜の形のような根は根茎以外は柔らかく、煮たりみそ漬けにしたりして食ベる。
私は田舎に住んで初めて、このキクイモと出合ったのだが、農村では昔から、野菜の一種として食ベられていたのだ。
私は食ベ 物よりも花に閲心があるのだが、多年草のこの植物は 恐ろしい<らいに増え続ける。二、三メートルの高さにもなり、太い茎や葉には、ざらざらとした突起がある。ついに悲鳴を上げて減らそうと思い、花の終ゎつた十月に根を掘り出した。ふと思い出して煮て食ベてみた。確かにお芋の昧はするけれど美昧しいとは言えない。次にみそ汁に入れてみた。周りの皮はジャガイモのようだが、中身は大根のようだ。賢治の母上のように、もっと料理を勉強しなければ。
アメリカの作家・ナチュラリストのダイアン・アッカーマンも、キクイモを植え替えようとして根をかじってみたという。昧はぱりぱりした石鹸のようだったというから、おいしくはなかったのだ。サラダにする人もいるらしいが、彼女はやはり、食ベることには興昧ないという。 彼女は花については何も述ベていない。
そういえば、キクイモのみそづけが好物だったという人がいた。宮沢賢治だ。
賢治は荒れた畑でキクイモを作り、三〇キロものキクイモを背負つて歩いたという。彼は詩にこう書いている。
「そもそも拙者ほんものの清教徒ならば」
(前八行略)
この荒れ畑の切り返しから
今日突然に湧き出した
三十キロでも利かないような
うすい黄色のこの菊芋
あしたもきっとこれだけとれ、
更に三四の日を保する
このエルサレムアーティチョーク
イヌリンを含み果糖を含み
小亜細亜では生でたべ
ラテン種属は煮て食べる (以下略)
詩を書き、童話を書き、農芸化学の教師であり農業に励んでいた賢治は、新しい物好きのモダンボーイだった。朋治初期に渡来したこの植物について、その成分さえも一九二〇年代にはすでに知っていたのだ。エルサレムアーテイチヨークは、キクイモの英語名である。ここにも賢治の舶来通があらわれている。
キクイモに関しては、私は団子より花だなぁ。キクイモはコスモスの花と同じ季節に、私の庭で競い合うが、どちらも繁殖カが強く、決してその場を譲らない。
私はどちらかといえば、増えて欲しいのはコスモスの花だ。実際にはコスモスも強い槙物なのだが、ゆらゆらと秋風に揺れる姿は繊細で弱々しく見える。つい情を誘われるのだ。 キクイモの花は、なんときっぱりとその力強さを顕していることだろう。
2021.10.10 旧編を再稿
ツィッター 2021.10.8
庭つくりで最初に植えたのが菊芋(キクイモ)の球根。花がとてもきれい。菊芋は宮沢賢治も畑で作り、母親の料理する精進料理のキクイモの味噌漬けを好んだ。

(拙著『宮沢賢治の菜食思想』料理の写真) キクイモはイヌりンという水溶性食物繊維が含まれているという。そのせいかイノシシが球根をよく食べる。
静かなる連載 「バカンスの夢」2021年9月
毎日が日曜日でも月曜日でもいい暮らしをしている私だが、咋年からのコロナ禍での自宅巣ごもり状態は苦しい。これまでは世間が休日ともなれば、滞在型のお客が多くなることも事実だし、私自身、雰囲気だけでも夏休みを楽しみたいではないか。しかし、お客がやって来ることと、海に近い田園に住んでいるので遠くに出かける必要のないのは、幸なのか不幸なのかどちらだろう?
そんなわけで私と夫の夏休みは、お客と一緒に夏休みするか、思い出や本によって遠くへ旅するのである。だが旅を憧れる心には、今年はふるさとの東京へさえ行かず、予定していた南仏プロブァンスへ行かれないことが悔しい。
プロブァンスと言えば、90年代に人気となった本の作者、イギリス人の作家ピーター・メイル氏と雑誌で対談した思い出が蘇る。それは春だった。
ある雑誌の仕事でメイル夫妻と東京でお会いしたが、その時、私はご夫妻に小さなプレゼントをした。どちらかというとミセス・メイル、すなわちジェニファーさんを心に入れて。
それは高さ十センチほどの小さな花束。朝六時、朝露をつけたままの春の野の花々を、私は野原や土手で摘んだ。それを小瓶に入れ、和紙で包み、リボンを掛けた。ホテルに着くと、カードと共にお部屋に届けたのである。
翌朝ご夫妻にお目にかかったとき、なぜか初対面ではないような雰囲気だった。ジェニファーさんは私を寝室まで引っ張っていき、「ねえ、見て、あそこに置いた
のよ」とサイドテーブルの上のあの小さな花束を示された。「きっとプロブァンスを思い出してくださると思って……」と私。
「ええ、その通り。芳わしい香りに、妻はとても喜んでいますよ」とメイル氏。
白い房咲き水仙を一本混ぜたら、菫や仏の座や姫踊り子草や、蔓十二単やブロ
ッコリーの〃プティット〃な花々に、密のような甘さが加わったブーケになったのである。
数日後、関西から戻ったジェニファーさんから手紙が届いた。彼女の、いかにもイギリス人らしい流麗なペン使いの手書きである。「ことのほかあの花束は嬉しかったです。押し花にしました。そして私の今回の旅の思い出帳に挟みました」とあった。
実は私は、こんな小さな花束を差し上げるなんて……と躊躇したのである。しかし夫は、「きっと喜んでくださるよ」、と贈る勇気を鼓舞してくれた。案の
定、お部屋はおびただしい数の大きな花束で溢れかえっていたのだった。それにもかかわらず、こんな小さな野の花にも喜び、敬意を表し、大切にしてくださったのである。一瞬にして散る花の命を、永遠にとどめて。私の胸に、熱いものが込み上げた。
私は贈物が下手である。あれこれ相手のことを想像し過ぎ、結局は自己満足で終わってしまうのが常であり、送ってしまってから、後悔することがしばしば。けれど今回だけは、こちらの思いの通じるよい受け手に出会え、贈り手としての私は幸せであった。
今頃あの花々は、私の代わりにプロヴァンスで素敵なバカンスを楽しんでいるのだろう。
ああ、それにしても、世界からコロナが消え去り、どんな人々とでも自由に幸せを分かちあえる日が、一日、一時間、一秒でも早く来ますように。
静かなる連載 「心の喫茶店」 21年10月7日
大人になる前の時期の、私の背景にはいつも、溜まり場としていた喫茶店があった。今思うと、私の人生の土台を築く一つの材料となったのが、喫茶店だったと言うとおおげさかな。若い頃に行っていた喫茶店のマスターの車椅子姿を遠くに見た時、そんな風に思った。
高校生の時、生まれて始めて入ったのは、北原白秋の詩集のタイトルと同じ名前の店「邪宗門」。小さい店内は、アンティークが所狭しと並び、青やピンクや黄色のランプシェードの幻想的な光で包まれている。その頃、こんなお店はどの町でも珍しかった。
そこへ行ったのは、現在のようなファーストフード店はおろか、他に喫茶店などなかったし、また学校から近かったからだ。
指定されて初めて入った喫茶店での本来の用事は、上級生の男子から、私の送ったラブレターに対する返事を貰うためだった。答えは「迷惑だからやめてほしい」。けれども私は、この夢か幻のような喫茶店を知り、通うようになったことの方を喜んだから、うちひしがれることもなく、挫けずに済んだ。
後になって私がアンティーク好きになり、また素人の喫茶店経営が流行ってきて私もそうしたいと願ったことは、不思議の国をかいま見た16歳のこの時に、端を発しているのだと思う。
その後大人になって、東京近郊の私のテリトリーだった二つの旧い喫茶店は、Hという同じ頭文字だった。
ついに私に、お客のために珈琲をたてる機会がきた。ある時、久しぶりにいつものジャズ喫茶店へ行ったらその店は壊され、大工さんではない普通の人たちが大工仕事をしているのである。「いったい、何をしているんですか?」
「自分たちの喫茶店を作っているんだ。あなたも仲間に入りませんか?」
気がつくと私は、すぐさまシャベルを握り、セメントをこねているのだった。毛皮のコートを着、九センチのヒールのブーツのままで。大学教授や評論家、歌手などといった人たちが参加し、やがて「ほんやら洞」と言う名の喫茶店が出来た。1年間そこにいた私は、とても大きなものを得たのである。
一生の生き方をどうするかと悩んでいた二十代、その頃出会った喫茶店は、自分たちの生き方を今までとは違うものにしようとする、いわゆる〃対抗文化〃を支持する人々の共同経営の店だった。ここに集まる人たちの自由さと闊達さに羨望はしたけれど、その中に飛び込んでいく勇気は出なかった。後にああ、やはり私はこの時から、彼らの思想や行動力の真価に気づいていて、真似ていたのだと知るが。
遠い国から運ばれて来る珈琲の豆。その豆をひき、一杯の珈琲を入れて飲む。それも家庭でなく喫茶店という独特の空間で。漂ってくるアロマは確かに珈琲豆のものなのだけれど、それはもはや豆自体のではなく、喫茶店のアロマでもある。その風味の中に、酸味や苦み、甘みが感じられるが、それはまた人生のアロマともなる。若き日の私の風味を作ってくれた喫茶店のマスターや仲間たち、彼らの年輪は、自分のそれでもあることを、今、毎日飲む私の心の喫茶店の一杯の珈琲が教えてくれる。



